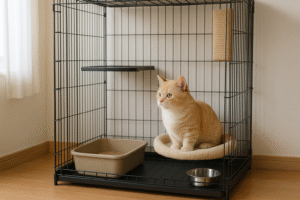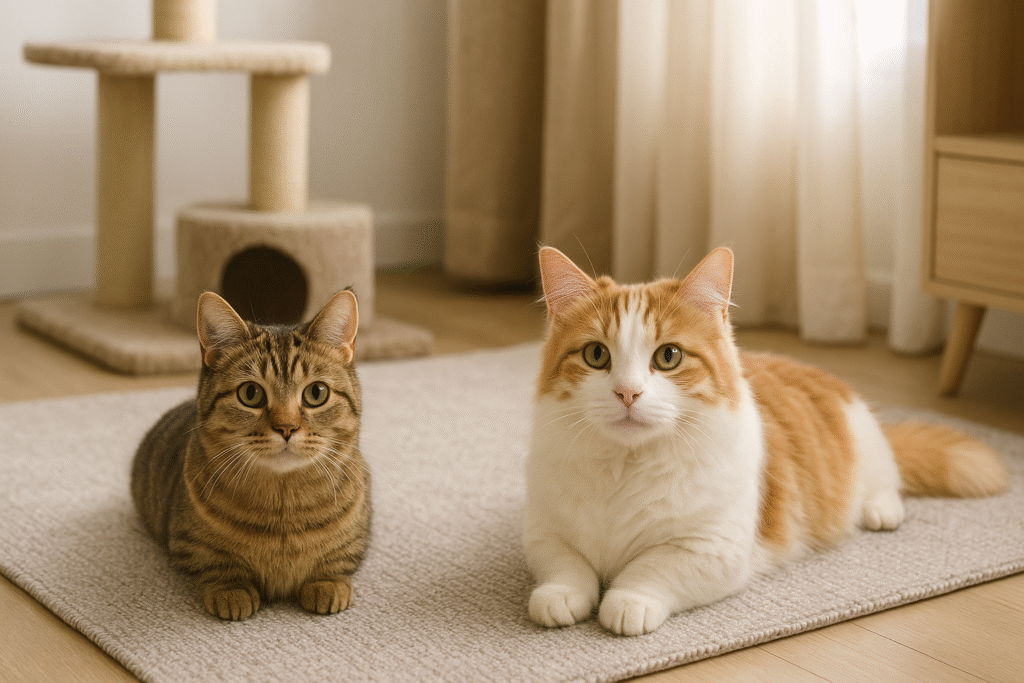
短足のかわいい姿が魅力のマンチカン。
しかし、「短足だと寿命が短い」と聞いて不安になる飼い主さんも多いのではないでしょうか?
この記事では、マンチカンの平均寿命や長足との違い、そして長生きしてもらうための具体的な飼育ポイントをわかりやすく紹介します。
マンチカンの寿命
短足マンチカンの寿命

短足のマンチカンは、その愛らしい姿で人気がありますが、実は「遺伝子の変異」によって足が短くなっている猫種です。
この特徴は骨軟骨異形成症(こつなんこついけいせいしょう)と呼ばれる遺伝的な要因と関係しており、体の構造上どうしても関節や背骨に負担がかかりやすい傾向があります。
そのため、短足マンチカンの平均寿命はおよそ10〜13年とされ、猫全体の平均寿命(約15年前後)よりやや短いのが一般的です。
また、遺伝的な要因から生まれてすぐに体調を崩す個体もいるため、平均値が短く見える場合もあります。
ただし、すでに1歳を超えて健康に育っている短足マンチカンであれば、15歳前後まで長生きするケースも珍しくありません。
飼育環境を整え、体への負担を減らす生活を心がけることで、寿命を延ばすことが十分に可能です。
長足マンチカンの寿命

長足のマンチカンは、短足の遺伝子を受け継いでいないため、体の構造上の負担が少なく、より健康的で長生きしやすい傾向があります。
平均寿命は12〜15年ほどと、一般的な猫の平均とほぼ同じか、やや長めです。
骨や関節のトラブルが起こりにくいぶん、運動能力も高く、健康管理さえしっかりしていれば高齢になっても元気に過ごせる個体が多いです。
とはいえ、長足のマンチカンでも肥満や腎臓病などの一般的な猫の疾患には注意が必要です。
マンチカンの病気対策
かかりやすい病気

マンチカンの特徴的な見た目から、いくつかかかりやすい病気をもっています。
特に短足・長毛といった人気のあるマンチカンほど体が弱くて病気にかかりやすいです。
病気になると看病する時間はもちろん医療費もかなり高くかかるので、飼い主としてはなるべくかかってほしくないですね。
ここで紹介する病気は、特にマンチカンにかかりやすいものです。
他にも猫のかかりやすい腎臓の病気やおしっこの病気などもあります。
骨軟骨異形成症
短足のマンチカンは短足遺伝子を持っています。
この短足遺伝子は遺伝の中で特別変異によって生じたもので、生物学的にはとても弱い立場にあります。
短足遺伝子をもったマンチカンは骨軟骨異形成症という病気にかかりやすいとされています。
これは、関節の中にある柔らかい軟骨が硬くなってしまう病気です。
この病気にかかると、猫は歩くのを嫌がったり触ると痛がったりするようになり、足にこぶのようなできものができることもあります。
治療は痛み止めなどの服薬が中心で、病気そのものを治すことはできません。
椎間板ヘルニア
短足のマンチカンでは長い胴体を支えるために背骨が無理をしてしまいます。
背骨の骨と骨の間にある椎間板という場所が変性して元の場所からはみ出してしまい、そのはみ出した部分が脊髄という神経を圧迫してしまう怖い病気です。
脊髄は手足を動かすための神経です。
そのため、椎間板ヘルニアになると足に麻痺が起こることがあります。
力が入りにくい様子だったり歩き方がいつもと違う様子があったりしたらこの病気の可能性があります。
歩くのが困難で、トイレに間に合わないということもあるようです。
毛球症
マンチカンの特徴として、短足だけでなく美しい長毛も挙げられます。
猫は基本的に自分で毛づくろいをして毛並みを保っていますが、毛づくろい中に毛をたくさん飲み込んでしまうと毛球症になってしまう危険があります。
毛球症になると、便秘や嘔吐、食欲不振などの症状がみられます。
そのままにしておくと、胃の中で毛が絡まり、詰まってしまうこともあります。

病気の予防

マンチカンは体の構造上、いくつかの病気にかかりやすい猫種です。
しかし、日々のケアや環境づくりによって多くの病気を防ぐことができます。
ここでは、代表的な予防のポイントを紹介します。
室内飼いで感染症を防ぐ
最も基本的で効果的な予防法は、完全室内飼いにすることです。
外に出ることで、ほかの猫との接触から感染症をもらうリスクが高まります。
また、交通事故や拾い食いによる中毒など、命に関わる危険もあります。
多くのマンチカンは“内弁慶”タイプで、外を見るのは好きでも外出は好まない子がほとんどです。
室内にキャットタワーや日当たりの良い窓辺を用意してあげると、ストレスなく安全に暮らせます。
避妊・去勢で病気とストレスを防ぐ
避妊・去勢手術は、病気の予防と性格の安定の両面から見ても大切なケアです。
発情期のストレスはホルモンバランスを崩し、泌尿器系の疾患や攻撃的な行動を引き起こすことがあります。
去勢・避妊を行うことで、これらのリスクを大きく減らすことができます。
雄の場合は前立腺疾患や睾丸腫瘍、雌の場合は子宮や卵巣の病気の予防に効果的です。
また、望まない出産を防ぎ、里親が見つからない子猫が増える社会的な問題の軽減にもつながります。
手術を受けたあとは代謝が落ちて太りやすくなるため、フード量を調整し、定期的な体重チェックを行うと安心です。
避妊・去勢によってストレスの少ない穏やかな性格になる子も多く、健康的な長寿にもつながります。
適度な運動で健康維持
マンチカンの健康を保つためには、無理のない運動が欠かせません。
活発で好奇心旺盛な性格を持つマンチカンは、遊びを通して心身の刺激を受けることで、ストレス発散にもつながります。
おもちゃや猫用トンネル、低めのキャットタワーを使った遊びは、短足のマンチカンにも負担が少なくおすすめです。
また、狩りごっこをイメージしたレーザーポインター遊びや、猫じゃらしを追いかける運動も効果的です。
安全な環境が整っていれば、階段の上り下りや短時間の散歩も良い運動になります。
ただし、関節や腰に負担をかけないよう、短い時間を1日数回に分けるのが理想です。
猫それぞれの性格や体調に合わせて、運動量を調整してあげましょう。
関節への負担を減らして骨軟骨異形成症を予防
マンチカン特有の病気である骨軟骨異形成症は、完全に防ぐことはできません。
しかし、関節に負担をかけない環境づくりで発症リスクを下げることは可能です。
短足のマンチカンは高い場所へのジャンプが苦手なので、低めのキャットタワーやスロープを設置してあげましょう。
フローリングには滑り止めマットを敷くと、足腰への衝撃をやわらげられます。

肥満対策で椎間板ヘルニアを防ぐ
椎間板ヘルニアは、肥満のマンチカンに多く見られます。
体重が増えると背骨への負担が大きくなり、神経を圧迫して歩行障害などを引き起こすことも。
食事量の管理と、栄養バランスのとれたフード選びが重要です。
特に去勢・避妊後は代謝が落ちやすいため、低カロリーフードに切り替えるなど工夫しましょう。
「食べたがるから可哀想」と思っても、健康のために心を鬼にして食事制限を行うことが長生きの秘訣です。

毛球症はブラッシングで予防できる
マンチカンは長毛の子も多く、毛球症(もうきゅうしょう)にかかりやすい猫種です。
毛づくろいの際に飲み込んだ毛が胃の中で溜まり、吐き気や食欲不振の原因になります。
これを防ぐためには、毎日のブラッシングが欠かせません。
長毛の子なら1日2回、短毛の子でも1日1回を目安に行いましょう。
特に換毛期(春・秋)は抜け毛が多くなるため、丁寧にブラシをかけてあげることが大切です。

定期的な健康診断で早期発見を
マンチカンは遺伝性疾患のリスクがあるため、年1回の健康診断は必須です。
できれば6歳を過ぎたら半年に1回を目安に行いましょう。
血液検査やレントゲン検査で関節や腎臓、肝臓の異常を早期に発見できます。
また、日頃から飼い主が「歩き方」「毛づや」「食欲」などを観察しておくと、ちょっとした変化にも気づけます。
異変を感じたらすぐに動物病院へ行くことが長生きの秘訣です。
短足の子も長足の子も、暮らし方次第で寿命は大きく変わります。
ここでは、マンチカンを少しでも長生きさせるための生活環境やケアのコツを紹介します。
まとめ
短足のマンチカンは体の構造上リスクが高いものの、生活環境を工夫することで十分に長生きが可能です。
段差を減らし、体重をコントロールし、定期的に健康診断を受ける。
この3つを心がけるだけで、愛猫の寿命は確実に伸ばせます。