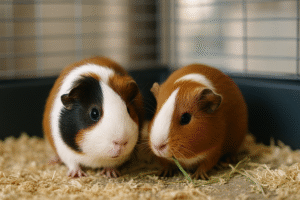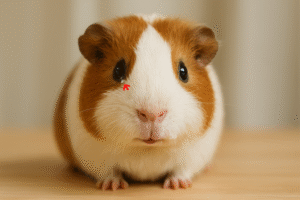モルモットを飼いたいけれど「夜行性でうるさいのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。
実際には飼い主の生活リズムに合わせて過ごすことができ、騒音対策も工夫次第で解決できます。
本記事では夜間の行動や生活音の実態、静かに暮らすための環境づくりについて解説します。
モルモットは夜行性なの?
飼い主に合わせて生活リズムを変える

モルモットは夜行性の動物として考えられていますが、飼われている人間の生活リズムに影響されて生活リズムを変える事が出来る動物です。
もともと、群れで生活をしている動物なので、仲間に合わせる生活を変化させていくことのできる能力を持った動物です。
迎え入れてくれた飼い主さんと同じようなリズムで入眠・起床します。
飼い主さんが規則正しい生活をしているのであれば、モルモットも同じように健康的な過ごし方が出来ると言う事です。
飼い主が不規則ならモルモットも影響を受ける

ですが、不規則な生活になるとモルモットも合わせようとするので、急な環境の変化にモルモットも影響されリズムが崩れてしまう事もあります。
人間が飼っているモルモットは、自分での生活リズムを作る事が難しい動物です。
モルモットの事を考えて生活リズムを整える

飼い主さんが出来る限り、モルモットの事を考えてあげる必要があります。
モルモットにも環境がしっかりと把握できるように、日の入りや日の出が分かりやすい所に小屋をおいてあげると生活リズムが整いやすいと言われています。
我が家のモルモットは、どちらかというと朝私が起きても、一度「おはよう」と小屋から出てきますが、少し経つとまた寝床でグーグー寝ている印象なので、マイペースなモルモットなのかと思っています。
仕事やテレビをみて夜更かしをしている時も、我が家のモルモットは起きて待っていてくれるので少し申し訳なさも抱きながらも夜更かししています。
そんな時は、膝に抱えて一緒にテレビを見たりパソコンでの仕事を行ったりします。
たまにする夜更かしをモルモットと共にしてみるのも面白いです。
夜行性モルモットとの暮らしで注意したい3つのポイント

夜間のケージ設置場所
モルモットは夜中に水を飲んだり牧草を食べたりするため、どうしても多少の物音は出ます。
寝室にケージを置いていると、その小さな音でも飼い主が眠れなくなることがあります。
夜間に静かに休みたい場合は、寝室から少し離れたリビングなどにケージを置くとよいでしょう。
ただし、孤独感を感じやすい動物なので、飼い主の気配が感じられる位置を選ぶことも大切です。
騒音を減らすための環境工夫
ケージに金網タイプの床を使うと、歩くたびにカタカタ音が響く場合があります。
床材をすのこやマットに変えるだけで大きく改善できます。
また、給水ボトルのポタポタ音が気になるときは、静音タイプの製品に替えるのも効果的です。
おもちゃやかじり木も金属や硬いプラスチック製より、木製や紙製の方が音が響きにくい傾向があります。
夜行性ゆえの遊び時間の工夫
モルモットは夜に活動する習性を持つため、昼間に十分遊ばせてあげないと、夜にエネルギーを発散しようとして動き回ることがあります。
夕方や夜の早い時間に散歩や遊びを取り入れることで、就寝時には比較的落ち着いて過ごしてくれるようになります。
飼い主が意識的に運動やコミュニケーションの時間を確保することが、夜の騒音対策にもつながります。
モルモットが出す騒音にはどんなものがあるか

モルモットは本来、食物連鎖の底辺近くにいる捕食動物の一種であったこともあり、とても臆病な動物です。
モルモットが出す騒音には、生活時の騒音もありますが泣き声も時には騒音になる場合もあります。
前項目でも記述しましたが、モルモットは飼い主さんに生活リズムを合わせることが出来る動物なので夜に騒音を出す事は殆どありません。
時に人間と同様に眠れない事はモルモット達にもあると思います。
その際に部屋の中を移動する音やおもちゃで遊ぶ音が気になる事はあると思いますが、人間と一緒と多めに見てあげてほしいなと思います。
我が家のモルモットは、時々夜中に餌を食べる音や水を飲む音などの生活音はありますが、さほど目立つものではありません。
臆病なモルモットに関しては、玄関チャイムの音や食器が重なる音などに驚いてしまい「グルグル」「キューキュー」など怒った様な泣き声を出すモルモットもいます。
日常の生活音には住み始めると慣れてくるとされますが、急に大きい音を出すと驚いてしまいますので、大きな音を出してしまった後に一声かけてあげると良いと思います。
モルモットは夜行性?の衝撃的真実!【まとめ】
モルモットは夜行性の習性を持ちますが、飼い主に生活リズムを合わせられる柔軟な動物です。
騒音も工夫次第で軽減でき、安心して一緒に暮らせます。
飼い主が規則正しい生活を心がけることが、モルモットの健康と静かな夜を守るポイントです。
詳しい飼育法は他の関連記事も参考にしてください。