
ポリプテルスは古代魚らしい姿で人気の高い観賞魚ですが、性格や大きさの関係から「他の魚と一緒に飼えるのか?」と悩む飼育者は少なくありません。
実際には混泳できるケースとできないケースがあり、相性を理解して水槽を立ち上げることが大切です。
本記事では、ポリプテルスの混泳の可否や注意点、相性の良い魚・悪い魚を具体的に解説していきます。
ポリプテルスの性格と混泳の基本

ポリプテルスは「古代魚」と呼ばれるだけあって独特な見た目をしていますが、性格面でも特徴的です。
基本的にはおとなしい魚で、自分から積極的に攻撃を仕掛けることは少ないといわれています。
しかし肉食魚であることに変わりはなく、自分の口に入るサイズの魚は捕食対象として見てしまうため、小型魚との混泳は難しいのが現実です。
また、縄張り意識はそこまで強くありませんが、底層で同じように泳ぐ魚との相性は悪い場合があります。
特に狭い水槽だと、餌を巡って小競り合いが起きたり、体をかじられるトラブルが発生することもあります。
混泳を考える際には「体格差」「性格」「遊泳層」の3つを意識することが重要です。
水槽内で生活リズムがかぶらず、かつ捕食のリスクが少ない相手を選ぶことが混泳成功の大前提になります。
ポリプテルスの種類による混泳相性の違い

ポリプテルスと一口にいっても、セネガルスのように30cm前後で収まる小型種から、ビキールやエンドリケリーのように70cm以上になる大型種まで幅広い種類が存在します。
そのため、混泳相手の選び方も種類ごとに注意が必要です。
小型種
小型種であるセネガルスやデルヘッジは、比較的おとなしい性格の個体が多く、同サイズ以上の中型魚との混泳が現実的です。
例えば、中型のプレコやナマズ類であれば捕食される心配が少なく、相性が良いケースが多くみられます。


大型種
一方で、エンドリケリーやビキールといった大型種は、成長すると小型魚だけでなく中型魚までも捕食してしまう可能性があります。


このクラスのポリプテルスと混泳させる場合は、アロワナやガーといった同じく大型の古代魚、あるいは大型プレコのようなタンクメイトが無難です。
また、アルビノやプラチナなどの改良品種は、基本的な性格は元となる種類と同じで、体色の違いによって混泳の可否が変わることはありません。
ただし、視認性が高いため他魚から執拗に追われるケースもあるので、レイアウトで隠れ家を十分に確保しておくと安心です。

混泳に向いている魚
ポリプテルスと混泳できる魚は、基本的に「体格が大きく、捕食されにくい種類」「水槽内で生活する層が違う種類」が向いています。
大型魚

まず代表的なのは、同じ古代魚であるアロワナやガーなどの大型魚です。
これらは水槽の上層を泳ぐ傾向があるため、底層で生活するポリプテルスとは棲み分けがしやすく、餌の取り合いも少なくなります。
シクリッド、ナマズ類

また、プレコやオスカーなどの中〜大型のシクリッド、ナマズ類も混泳候補になります。
特に大型プレコは水槽の掃除役にもなり、ポリプテルスと相性が良いケースが多いです。
同種同士
アクアリウムあるある✨✨✨
— ねぎちゃん@アクアリウムあるある (@Integra__dc5__) August 31, 2025
ポリプテルスを見てよく言われる言葉
第3位 どじょう?うなぎ?
第2位 生きてる?
第一位 なんで同じ魚ばっかり飼ってる
の?
わかる〜♪ pic.twitter.com/nnzguiENFn
さらに、同種同士の混泳も可能です。
ただしポリプテルス同士であってもサイズ差が大きいと、小さい個体が餌として認識される可能性があるため、導入時は体格をそろえることがポイントです。
混泳が難しい・避けた方がいい魚
小型魚
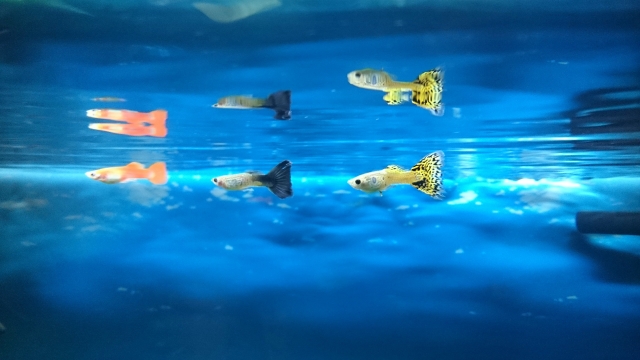
ポリプテルスは肉食魚であるため、小型魚との混泳は基本的に不可能です。
グッピーやネオンテトラ、ラスボラといった熱帯魚は、体長が小さいためすぐに捕食対象となってしまいます。
見た目には仲良く泳いでいるように見えても、ある日突然いなくなるケースが多いため注意が必要です。
ヒレが目立つ魚

また、ヒレが大きくひらひらと目立つ魚も避けた方が良い相手です。例えばエンゼルフィッシュやベタなどは、ポリプテルスにヒレをかじられやすく、ストレスや病気の原因となってしまいます。
気性の荒い魚
アフリカンシクリッド pic.twitter.com/RqL8yvgH1j
— クレニキクラマン (@calummaaiai) June 8, 2025
さらに、気性の荒い魚も混泳には向きません。
アフリカンシクリッドなど攻撃的な種類は、ポリプテルスを突いたり傷つけてしまうことがあり、逆におとなしいポリプテルスが弱ってしまうこともあります。
つまり「小さすぎる魚」「ヒレが目立つ魚」「攻撃性が強い魚」の3タイプは混泳が難しいと覚えておくと安心です。
混泳を成功させる3つのポイント

ポリプテルスとの混泳を成功させるためには、相手選びだけでなく「飼育環境の工夫」も大切です。
水槽サイズ
まずは水槽サイズです。
小さな水槽ではテリトリー争いや餌の取り合いが起きやすくなります。
ポリプテルスは成長すると体長が30cmを超えるため、最低でも90cm水槽以上、大型種の場合は120cm以上を用意するのが望ましいです。
レイアウトの工夫
次にレイアウトの工夫です。
流木や岩を配置して隠れ家を複数つくると、魚同士の視線が遮られ、無用な小競り合いを減らせます。
底層で生活するポリプテルスは、身を隠せる場所があることでストレスが軽減され、混泳相手との距離感を保ちやすくなります。
餌の与え方
また、餌の与え方も重要です。
ポリプテルスはゆっくりと底に沈む餌を好みますが、上層や中層を泳ぐ魚は素早く餌を食べてしまうことがあります。
餌が行き渡らないとポリプテルスが痩せてしまうため、沈下性の餌を選んだり、夜間に餌を与える工夫をするとトラブルを回避できます。
このように、水槽サイズ・レイアウト・餌の与え方を工夫することで、混泳の成功率を大きく高めることができます。
混泳トラブルが起きたときの対処法

混泳を始めた当初は問題がなくても、成長や環境の変化によってトラブルが発生することがあります。
特にポリプテルスは肉食魚であるため、体格差が出てきたときに捕食行動が起きやすく注意が必要です。
もし怪我をしたりストレスで弱っている個体を見つけた場合は、すぐに隔離して別水槽や隔離ケースで療養させましょう。
水槽内で追い回され続けると体力が消耗し、病気につながることがあります。
また、トラブルが頻発する場合には、水槽の仕切りを使ってエリアを分ける方法も有効です。
同じ水槽内でも物理的に接触を避けられるため、相性が悪い個体同士を無理に分けなくても済みます。
それでも改善されない場合や明らかに捕食される危険がある場合は、思い切って別々に飼育する方が安全です。
一度攻撃や捕食行動が習慣化すると、再び同じ水槽に戻しても関係が改善することは少ないためです。
混泳は「絶対に成功する」というものではなく、失敗のリスクを常に考えて対応できる準備をしておくことが大切です。
まとめ
ポリプテルスは基本的におとなしい古代魚ですが、肉食性を持つため小さな魚は捕食対象になりやすく、混泳には注意が必要です。種類によって最大サイズが大きく異なり、セネガルスやデルヘッジのような小型種と、エンドリケリーやビキールといった大型種では相性の良い相手も変わってきます。
混泳がうまくいきやすいのは、同じく大型の古代魚や中〜大型のナマズ・プレコ類であり、逆に小型魚やヒレをかじられやすい魚、攻撃的な魚との同居は避けるべきです。
また、水槽サイズを大きめに用意し、隠れ家を増やすことや餌の与え方を工夫することで、トラブルの発生を抑えられます。それでも問題が起きた場合は、隔離や仕切りの利用、最終的には別水槽での飼育も検討する必要があります。
つまりポリプテルスの混泳は「種類やサイズ差、環境の工夫次第で可能だが、常にリスクがある」という点を理解しておくことが成功のカギです。



