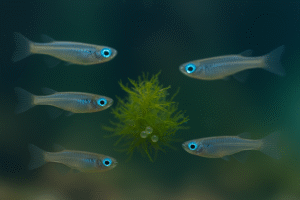熱帯魚が死んでしまったとき、ショックでどうすればいいのかわからなくなる方も多いでしょう。
しかし、そのままにすると水質の悪化や他の魚への感染につながる危険性があります。
この記事では、熱帯魚が死んだときにすぐに取るべき行動と水槽管理の流れを解説します。
熱帯魚が死んだらまず何をする?

熱帯魚が死んでしまったとき、気持ちが動揺してしまうのは当然のことです。
ですが、適切に処理しないと水槽環境や他の魚に悪影響を及ぼす可能性があります。
冷静に以下の点を確認してみましょう。
すぐに死体を取り出す
死んだ魚をそのままにすると水質が急激に悪化します。
アンモニアが発生し、残っている魚の命をも危険にさらすため、できるだけ早く網などを使って取り出しましょう。
体の状態を観察する
死んでしまった魚の体を観察して、病気やケガの跡がないかを確認します。
白いカビのようなものが付着している、ヒレが裂けている、体に赤い斑点があるなどの場合は病気や水質悪化が原因かもしれません。
これを見極めることで、水槽内に同じリスクが残っていないか判断できます。
水槽全体のチェックを行う
温度計・フィルター・エアレーションの動作を確認し、水質(水温・pH・アンモニア濃度)が急変していないかを調べましょう。
他の魚に異常が出ていないかも観察し、必要に応じて部分的な水換えや水槽のリセットを検討します。
処分方法|熱帯魚が死んだらどうする?
生ごみとして処分が一般的

かわいそうですが、死んだら魚はただの死骸でしかありません。
あまり情に流されず、生ごみとして処分しましょう。
トイレに流してもいいの?
小型の熱帯魚の場合、「トイレに流してしまっても大丈夫?」と考える方もいます。
確かに昔はトイレ処分が一般的だった時代もありますが、現在では注意が必要です。
小型魚なら流せるケースもある
グッピーやネオンテトラなど、ごく小さな魚であればトイレに流すことは物理的には可能です。
密閉できるビニール袋が手元にない場合や、すぐに処理したいときの手段として用いられることもあります。
感染症リスクと環境への影響
ただし、魚が病気で死んでいた場合、排水を通じて病原菌が広がるリスクはゼロではありません。
また下水処理場で処理されるとはいえ、衛生面で完全に安全とは言い切れません。
そのため、自治体によっては「トイレに流す処分は禁止」としている地域もあります。
基本は生ごみ処分がおすすめ
トイレ処分はあくまで最終手段であり、一般的にはビニール袋に包んで生ごみとして捨てるのが望ましいです。
どうしてもトイレに流す場合は、死んで間もない小型魚だけに限り、流した後はトイレ周りをきちんと清掃するなど衛生管理を徹底しましょう。
庭に埋めるのはおすすめしません

何らかの感染症をもっているとこわいので、自宅の庭に埋めて処理するのはおススメしません。
もちろん、近所に池や川があっても流してはいけません。
人間以上に、その場所にすむほかの生き物に影響を与えてしまうためです。
公共の場所に埋めるのは違反行為

また、公園など公共の場所に飼育していた生き物を埋めるのは犯罪です。
また、死んだ魚を肉食魚の餌にする人もいるようですが、これも与えた肉食魚に何らかの病気が感染したり、食べなれていないものを食べたことで健康を害する恐れがあるのでやめたほうがいいでしょう。
キッチンペーパーや新聞紙でくるみ、ビニール袋に密閉して捨てましょう。
小型魚ならトイレに流すのも有効です。
残念ですが、火葬すると骨が残らないため、ペット霊園では引き取ってもらえません。
標本にするのもあり

技術のある人なら、骨格標本やはく製、液浸標本にすることもできます。
死体を引き取って標本にしてくれる業者さんもいるので、そういった希望があるのなら探してみましょう。
何を冷酷な、と思うかもしれませんが、飼っていた魚の標本を飾るのも悪くないものです。
私も、思い入れのあったアロワナが死亡した際に友人に頼んで骨格標本を作ってもらいました。
美しい上に躍動感のあるポーズにしてもらえて、今でも部屋に飾っています。
熱帯魚が死んだときに確認すべきこと

魚が死んでしまったら、ただ処分するだけでなく「なぜ死んでしまったのか」を冷静に確認することが大切です。
原因を探ることで、残された魚を守ることにつながります。
寿命や自然死の可能性を見極める
小型魚は1〜3年、大型魚は10年以上と種類ごとに寿命が違います。
繁殖から長く飼っていた個体であれば、自然死である可能性が高いでしょう。
この場合は特別な対策は不要ですが、水槽環境の見直しをしておくと安心です。
病気や水質悪化が原因のケース
白点病や水カビ病など、病気が原因で死んでしまうケースも多くあります。
また、フィルターの停止や水換え不足によるアンモニア中毒など、水質トラブルが原因になることも。
死んだ魚の体表に白い斑点、カビ状の付着物、赤みや腫れがあれば病気を疑いましょう。
飼育環境による事故死のチェック
飛び出し事故や、ヒーターのトラブルによる水温上昇、同居魚とのケンカで致命傷を負うこともあります。
こうしたケースでは残りの魚が同じ被害に遭わないよう、フタの設置や水温計の管理、混泳相性の見直しが必要です。
熱帯魚が死んだら元の水槽はどうする?

もし単独飼育していた魚が死亡して、もう魚を飼う予定がないのなら、お住まいの地域の規定に沿って水槽を処分しましょう。
問題は、複数飼育していてまだ魚を飼い続けている場合や、もう一度その水槽で魚を飼いたい場合です。
実際には、このケースがほとんどだと思います。
理想的には、水槽をリセットすべきです。
もし、死亡した魚が病死だった場合、次に入れた魚やほかの魚に感染するリスクがあるためです。
まだ飼っている魚がいる場合はいったん別の水槽にうつし、水草や床材、ろ材はすべて捨てるか熱湯消毒、水槽とフィルターも天日干しします。
単独飼育していたのなら元の水槽は空なのでこういった対応も可能ですが、たとえばレイアウト水槽で小型魚の群れを飼っていて一匹だけ死んだ場合、水槽のリセットは現実的ではないと思います。
この場合は少し様子をみましょう。
小型魚なら寿命で突然死ぬことはよくあることです。
しばらく様子を見てほかの魚に異常がないのなら、そのまま飼育し続けて大丈夫でしょう。
小型水槽で少数の小型魚を飼育していたのなら、新品の水槽を立ち上げてそちらに魚を引っ越しさせる方法もあります。
使っていた水槽を消毒するよりも新しい水槽を立ち上げる方が楽なので、スペースが許すならこのほうがいいでしょう。
なお、魚が死んだからといって急に大量の水替えをするのはあまり意味がありません。
もし病死だった場合、水替えをしたくらいで病原菌が消えることはありません。
特にほかの魚をまだ飼育しているのなら、かえって体調を崩す原因になってしまいます。
普段通り飼育して様子を見るか、徹底的にリセットするかの二択です。
熱帯魚が死んだらどうするの?【まとめ】
熱帯魚が死んでしまったら、まずは死体を取り出し、体の状態や水槽環境を確認しましょう。
病気や事故死なのか寿命なのかを見極めることで、残った魚を守ることができます。
悲しい出来事ではありますが、適切な対処が次の飼育に活かされます。