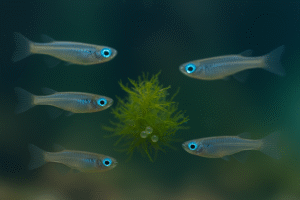熱帯魚を飼っていて引越しを控えている方にとって「魚はどう運ぶ?」は大きな不安材料。
特に小型魚であればペットボトルを使った方法が手軽ですが、注意点もあります。
この記事では、ペットボトルを使った輸送のメリット・デメリット、酸素対策や温度管理の工夫、さらに大型魚の引越しに役立つパッキング方法や専門業者への依頼についてもまとめました。
調べたところ熱帯魚の引越しにはペットボトルを使用するのが楽!という情報がありましたのでご紹介します。
熱帯魚の引越しにペットボトルの方法

事前準備
引越し直前に行うと失敗やどうしてもバタバタしてしまいますので、1週間前位から準備を始めましょう。
熱帯魚のパッキングなどは引越し2日前位に用意しておくと良いでしょう。
熱帯魚の餌は引越し3日前位から絶食させます。
これは輸送時のフンによる水質悪化を防ぐために行いましょう。
冬場や移動距離の長い引越しの場合は、急激な水温変化による負担を減らす目的で1週間くらいかけてヒーターの温度を徐々に下げておきましょう。
事前に引越し業者に熱帯魚が運べるのか、見積もりの際に聞いておくことも忘れずに。

水を抜いた水槽や機器は運べることが多いのですが、生体は運べないことが多いようです。
荷物だけ業者にお願いして、熱帯魚だけ自分で運べれば良いのですがそうはいかないことも多いです。
飛行機ならば小型の熱帯魚であれば手荷物で運べるようです。
- 1週間前 ヒーターの温度を徐々に下げていく
- 3日前 絶食
- 2日前 パッキング
ペットボトルのサイズについて
基本的には 大きめのサイズ(1.5L〜2L程度) を使った方が安心です。
理由は以下の通りです。
- 水量が多いほど水質悪化が遅くなる
- 水温変化のスピードが緩やかになる
- 魚が動けるスペースが確保できる
小型魚(ネオンテトラ、グッピーなど)であれば500mlでも不可能ではありませんが、余裕を持たせるなら1L以上がおすすめです。
ペットボトルサイズと魚の匹数
注意したいのが、ペットボトル1本に入れる匹数です。
2Lサイズのペットボトルを使う場合でも、あまりたくさんの魚を入れるのは危険です。
例えばネオンテトラやグッピーのような体長3cm前後の小型魚であれば5〜6匹ほどが目安です。
メダカならもう少し入れられますが、それでも8匹程度までにとどめた方が安心です。
コリドラスやプラティなど少し大きめの魚は2〜3匹に分けて入れるのが無難です。
匹数が多いと酸素不足や水質悪化が急速に進むため、必ず複数のペットボトルに分けることを心がけましょう。
ペットボトルの飲みものの種類について
実は使うペットボトルの種類も重要です。
最も安全なのは水や無糖・ノンカフェインのお茶(麦茶等)が入っていたものです。
炭酸飲料やジュースの容器は糖分や香料がプラスチックに残りやすく、洗っても完全に取れないことがあります。
スポーツドリンク系も塩分やミネラルが残る可能性があるため避けましょう。
結論としては、新品または水用・お茶用のボトルを使うのがベストです。
ペットボトルに入れる水
ペットボトルに入れる水は、必ず水槽の飼育水を使うのが基本です。
魚がすでに慣れている水質であれば、輸送時のストレスを大きく減らせます。
飼育水を使わずに新しい水を入れてしまうと、水質の急な変化が原因で体調を崩す恐れがあるため注意が必要です。
どうしても飼育水だけでは量が足りない場合は、カルキ抜きをした水道水を補助的に加えても構いません。
ただしその場合も、できるだけ飼育水を多めに確保しておくことが理想です。
引越し先で新しい水槽を立ち上げる際にも、持ち運んだ飼育水を使うことで魚がスムーズに新環境へ適応できます。
輸送の負担を軽くし、引越し後の立ち上げを助ける意味でも、飼育水は可能な限り多めにペットボトルで運ぶようにしましょう。
水位(空気のスペース)について
ペットボトルに入れる水(水槽の水)はギリギリまで入れてはいけません。
必ず空気の層を残すことが大切です。
- 魚は水中の酸素をエラで取り込みますが、輸送中は水中の酸素がすぐに減ってしまいます。
- ペットボトルの上部に空気を残すことで、移動中に魚が水面から酸素を取り込みやすくなります。
- 目安としては 水:空気 = 7:3 くらい が理想です。
運び方は?
ペットボトルには水槽の飼育水や水草を入れておきましょう。
熱帯魚の種類によってはペットボトルに入らないものもいます。
もちろん小型の魚ならばペットボトルに入れて運んだ方が楽なので、ペットボトルに入れても良いです。
ペットボトルに飼育水を入れて良い、というのは引越し後の魚の負担を減らすためです。
新たに水槽を立ち上げるとなると、水質が一気に変わり熱帯魚の負担になります。
最悪死んでしまうこともありますので、飼育水は多めに確保しておくと良いでしょう。
ペットボトル輸送のメリットと注意点
メリット|手軽さと費用を抑えられる
ペットボトルを使った輸送は、特別な器具を用意しなくても手元にある素材で準備できる点が最大のメリットです。
小型魚であればペットボトルに収まるため、梱包の手間が少なく、短距離の引越しなら十分対応可能です。
また費用もほとんどかからず、コストを抑えながら引越しができます。
デメリット|対応できる魚が限定される
一方で、ペットボトルに入れられるのは小型魚に限られます。
エンゼルフィッシュや大型のナマズ類など体長がある魚は狭い容器に入れるとストレスや怪我の原因になります。
また水量が少ないため酸素不足や水質悪化が早く進む点も注意が必要です。
酸素・温度管理の工夫
移動時間が2〜3時間程度ならそのままでも大きな問題はありませんが、長時間の移動では酸素不足に陥る可能性があります。
市販の酸素石や、数本のペットボトルに分けて飼育水を確保すると安心です。
また夏場は高温、冬場は低温で魚に大きな負担がかかるため、発泡スチロールやクーラーボックスに入れて温度を安定させましょう。
熱帯魚の引越しにはパッキングもおすすめ

ペットボトルで運ぶ場合は小さい熱帯魚限定となります。
ペットボトルに入らないサイズの熱帯魚を運ぶ際はビニールパッキングがおすすめです。
金魚すくいで持ち帰るときに使うものをイメージしてもらうと分かりやすいです。
方法はビニール袋に多めに飼育水と熱帯魚を入れ、輪ゴムで止めます。
とげのある熱帯魚の場合は袋を3重位にしておくと安心です。
短時間の移動でしたら、そのままで問題ありません。
時間がかかる、異動距離が長い場合は酸素が必要になります。
市販の酸素ボンベで酸素を入れるか、酸素の出る石を用意しましょう。
熱帯魚の引越しでペットボトルとパッキングが終わったらこれで終わりではありません。
引越しの時期によりますが、保温や加温が必要な場合があります。
特に加温や保温が必要ない場合はパッキングした熱帯魚を、段ボールに入れても大丈夫です。
夏場の保温はクーラーボックスか発泡スチロールにいれておくと良いでしょう。
冬場は加温が必要になります。
クーラーボックスや発泡スチロールに、カイロを何枚か入れて置きましょう。
他の熱帯魚の引っ越し方法
自分で用意するのが心配、手間な場合はアクアショップや専門業者に頼むのも良いでしょう。
コストはかかりますがこれが熱帯魚にとって一番安心で安全です。
ネットで【熱帯魚 引越し 業者】などで検索するといくつかヒットします。
大型の熱帯魚や、飼育が難しいような熱帯魚などはこちらを頼むと良いでしょう。
熱帯魚のペットボトルでの引っ越しはどこまでが現実的?

近距離+小型魚ならペットボトルの引っ越しが可能
ペットボトルを使った熱帯魚の引越しは、あくまで短距離・短時間の輸送に限定されます。
小型魚を数匹程度、数時間以内に運ぶのであれば、水と空気をバランスよく入れたペットボトルで問題ありません。
特に自家用車での近距離引越しなら現実的な方法といえるでしょう。
長距離移動や大型魚は他の方法を
しかし半日以上かかるような長距離の移動では、ペットボトルでは酸素不足や水質悪化が避けられません。
その場合はショップと同じように袋パッキングに酸素を充填する方法が必要です。
酸素ボンベは一般の飼育者でもネット通販などで入手可能ですが、価格は数千円〜2万円ほどかかり、一度きりの引越し用としては現実的ではありません。
熱帯魚の引っ越しはペットボトルでできる?【まとめ】
熱帯魚の引越しは一見難しそうですが、ペットボトルやパッキングを工夫すれば自分でも対応可能です。
ただし魚の大きさや距離によって最適な方法は異なるため、状況に合わせて選択しましょう。
引越し後は水質や温度を安定させることが最も重要です。無理に自力で行うよりも、必要に応じて専門業者に依頼する選択肢も検討してください。
魚たちが新しい環境でも元気に過ごせるよう、丁寧な準備を心がけましょう。